よりよい特許は、
お客さまに寄り添う
品質重視の特許事務所から
Read More事務所案内
ご挨拶
私たちサンライズ国際特許事務所は、平成8年(1996年)に設立されましたが、設立当初から、お客さまの利益を最優先に考え、高品質の商品(特許庁への提出書類などです。)を生み出すことが使命であると心して仕事に邁進して参りました。
業務案内
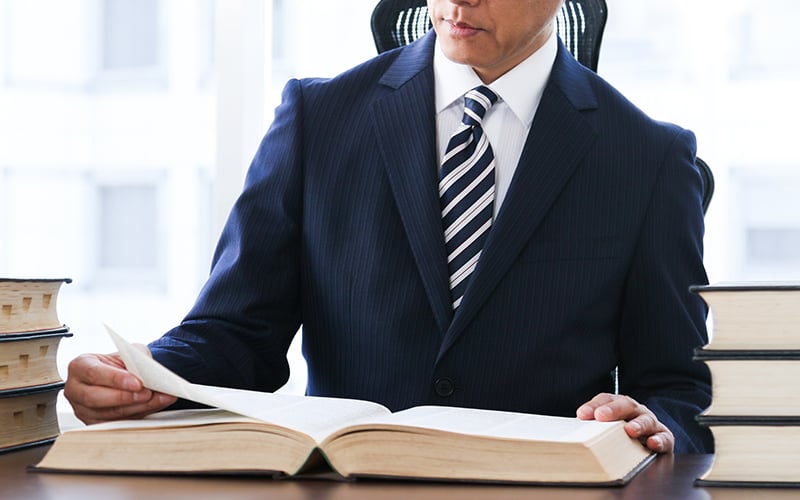
国内特許の取得

外国特許の取得

商標・意匠登録
特許事務所をお探しの方
初めて特許取得を
ご検討の方へ
新たな特許事務所を
お探しの方へ
新着情報
AI関連発明[第20回]:これからのAI開発と知財の役割 ― 中小企業が勝ち残るために
◆はじめに AI技術は、今後のあらゆる産業において中核的な役割を果たすことが確実視されています。大企業が潤沢な資金と人材を武器にAI研究を加速させる一方、中小企業もまた、自社の業務や製品にAIを取り入れることで競争力を強化し、新たな市場を切り開くチャンスを得ることができます。 1. 中小企業がAIを活用する意味...
AI関連発明[第19回]:海外展開時のAI特許戦略(米国・中国・欧州)
◆はじめに AI関連技術をグローバルに展開するにあたって、国内での特許取得だけではなく、米国・中国・欧州という主要地域での知財戦略を如何に構築するかが重要です。各地域ごとに制度・審査実務・ライセンス環境が異なるため、それぞれの特徴を理解し、戦略的に対応する必要があります。 1. 米国での戦略ポイント 米国では、United States Patent and Trademark Office(USPTO)によるAI・ソフトウエア関連出願の審査において、35 U.S.C. §101(特許適格性)が重要な論点となります。...
AI関連発明[第18回]:AI特許に関する訴訟事例から学ぶべきこと
◆はじめに AI技術の進展に伴い、AI関連の特許をめぐる訴訟も国内外で増加しています。これらの訴訟事例からは、単なる特許取得だけでなく、特許の活用や管理、契約・ライセンス戦略まで含めた知財戦略全体の重要性が浮き彫りになります。 1. AI関連訴訟の傾向 近年のAI関連特許訴訟には、以下のような特徴が見られます: ・アルゴリズムや推論処理の構成が争点となるケース ・データ処理・機械学習モデルの実装方法に関する侵害主張 ・スタートアップと大企業間での係争が増加傾向 ・学習済みモデルやクラウドAI...
AI関連発明[第17回]:AI関連特許のライセンス活用例と契約の注意点
◆はじめに AI技術の急速な普及により、特許の保有だけでなく、そのライセンスを通じた活用も重要な戦略の一つとなっています。AI関連発明について他社とライセンス契約を締結することで、新たなビジネスモデルの創出や技術連携が可能となる一方、契約上の注意点も多く存在します。 1. ライセンス活用の目的とパターン AI関連特許のライセンス活用には以下のようなパターンがあります: ・自社特許を他社に使用させる(アウトライセンス) ・他社特許を使用する許諾を得る(インライセンス) ・クロスライセンス契約による相互使用...
AI関連発明[第16回]:他社特許への抵触リスクと回避設計のポイント
◆はじめに AI技術の活用が進む中、自社の製品やサービスが他社の特許権を侵害してしまうリスクにも十分に注意を払う必要があります。特に技術開発のスピードが速く、似たような技術が多数出願されているAI分野では、他社特許との衝突を回避するための戦略的設計が重要です。 1. 他社特許のリスクとは...
ブログ
AI関連発明[第20回]:これからのAI開発と知財の役割 ― 中小企業が勝ち残るために
◆はじめに AI技術は、今後のあらゆる産業において中核的な役割を果たすことが確実視されています。大企業が潤沢な資金と人材を武器にAI研究を加速させる一方、中小企業もまた、自社の業務や製品にAIを取り入れることで競争力を強化し、新たな市場を切り開くチャンスを得ることができます。 1. 中小企業がAIを活用する意味...
AI関連発明[第19回]:海外展開時のAI特許戦略(米国・中国・欧州)
◆はじめに AI関連技術をグローバルに展開するにあたって、国内での特許取得だけではなく、米国・中国・欧州という主要地域での知財戦略を如何に構築するかが重要です。各地域ごとに制度・審査実務・ライセンス環境が異なるため、それぞれの特徴を理解し、戦略的に対応する必要があります。 1. 米国での戦略ポイント 米国では、United States Patent and Trademark Office(USPTO)によるAI・ソフトウエア関連出願の審査において、35 U.S.C. §101(特許適格性)が重要な論点となります。...
AI関連発明[第18回]:AI特許に関する訴訟事例から学ぶべきこと
◆はじめに AI技術の進展に伴い、AI関連の特許をめぐる訴訟も国内外で増加しています。これらの訴訟事例からは、単なる特許取得だけでなく、特許の活用や管理、契約・ライセンス戦略まで含めた知財戦略全体の重要性が浮き彫りになります。 1. AI関連訴訟の傾向 近年のAI関連特許訴訟には、以下のような特徴が見られます: ・アルゴリズムや推論処理の構成が争点となるケース ・データ処理・機械学習モデルの実装方法に関する侵害主張 ・スタートアップと大企業間での係争が増加傾向 ・学習済みモデルやクラウドAI...
AI関連発明[第17回]:AI関連特許のライセンス活用例と契約の注意点
◆はじめに AI技術の急速な普及により、特許の保有だけでなく、そのライセンスを通じた活用も重要な戦略の一つとなっています。AI関連発明について他社とライセンス契約を締結することで、新たなビジネスモデルの創出や技術連携が可能となる一方、契約上の注意点も多く存在します。 1. ライセンス活用の目的とパターン AI関連特許のライセンス活用には以下のようなパターンがあります: ・自社特許を他社に使用させる(アウトライセンス) ・他社特許を使用する許諾を得る(インライセンス) ・クロスライセンス契約による相互使用...
AI関連発明[第16回]:他社特許への抵触リスクと回避設計のポイント
◆はじめに AI技術の活用が進む中、自社の製品やサービスが他社の特許権を侵害してしまうリスクにも十分に注意を払う必要があります。特に技術開発のスピードが速く、似たような技術が多数出願されているAI分野では、他社特許との衝突を回避するための戦略的設計が重要です。 1. 他社特許のリスクとは...
